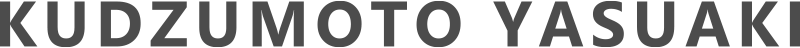2020年、「維持される気配」というテーマに関して
東京オリンピックの開催に伴い、日本にとっては記念すべき年となる予定であった2020年。新型コロナウイルス感染症が猛威を振るい、世界的に生命活動の存続が危ぶまれるなど、誰が予想し得たであろう?感染者数、死者数はいまだ留まるところを知らず、各地での文化イベントの開催も中止、延期が相次いでいる。全国、全世界中の美術館やギャラリーが閉館、自粛を迫られた中で、当然、本展覧会にもその影響が与えられたことは言うまでもない。日々変わるような変わらないような情勢を眺めつつ、企画自体の可否や実施方法、鑑賞者の動向、そして作品の中身や見え方に対して与えられた影響を許容し俯瞰してみれば、2020年に生きる私たちが剥き出しにされたような展示となったように思う。その中でも特筆して示しておきたいことは、展示室1が「作品同士がソーシャルディスタンスを取っているようだ」ということだ。本来グループ展といえば、異なる作家同士の関連性や連続性、同じ空間にある作品の相互的な介入・干渉が肝となる。しかし、今回の展示室1の作品配 置は壁やガラスケースで完全に仕切られ、 徹頭徹尾それぞれがそれぞれに独立し、まるで自分の殻に閉じこもるように“自粛”している作品たちだ。まるで今の時代の在り方を象徴しているような配置となった。
さて、今回テーマとした「維持される気配」。それは私たちが無意識下で行なっているささやかな生命活活を、反芻し、重ね、交えることで、確かな手応えとして立ち起こそうとする試みである。その”無意識的なささやかな生命活動”は、例えば呼吸をすることや、衣服を着ること、モノを消費すること。あるいは太陽や重力に従って、誰かや自然と関わり合いを持つことなどである。作品を通しそれらを知覚できた時、私たちは新たな視点を持って世界や自身の物事を理解することができるだろう。
今回紹介した3名は、”気配”を確実な物質としてでの痕跡ではなく、より一層漠然とした空気感として捉えようと制作している。その空気感は、”気配”の主体の外側にある空間や、それを視認した者の感覚の記憶とも言い換えられる。それらを現す際、彼らは 非常にあっさりと軽やかなビジュアルとして打ち出してくる。しかしそれは観れば観るほど、覗けば覗くほどに、複雑なものとして意識化されていくであろう。一見すると極めて私的かつロマンチックでドラマチックでありながら、それらは全て生々しい私たちの現実である。そこに印されるものは生物としての息遣いであり、体温であり、細胞や神経や筋肉の動きといった基本的な生命活動の形跡であると同時に、ホモサピエンスとしてでなく、哲学的に思考し生きる人間として行う営みでもあるのだから。
ところで、新型コロナウイルス感染症の時代になって、様々な物事に対する認識が一変するなど、昨年までは一切考えてもみなかった。そこで今回の展示では、前述したように各作家はそれぞれに、幾つかの作品を制作するにあたって新型コロナウイルス感染症を考慮し、非常にセンシティブなアプローチを行なった。
中でも顕著に現れたのが、犬飼の「Breathing Harmony」である。「Breathing Harmony」は1997年から制作を続けている、彼女の呼吸によるコミュニケーションを提示する作品だ。展示室2の映像でドキュメントされている通り、彼女は他人と同じ空間で、同じ空気を吸って吐く。犬飼自身も、そして私たち鑑賞者も、「呼吸」や「共有される空気」に対し、昨年までは非常にフラットな意味合いを持ってそれを捉えていたであろう。しかし、新型コロナウイルス感染症が飛沫感染をするために、それらに対し、マイナスイメージが付随されてしまう時代になってしまった。そこで今回犬飼は、あえて一人で展示ケース内に篭り、数日間をかけて今まで彼女が積み重ねてきた人との出会いを追想しながら、現在の呼吸を重ね合わせていく作品の制作にあたった。まるで彼女自身の過去作品を新たにオマージュするように。それは相手が不在のままに、自身と他者とのコミュニケーションを確認し直す行為であり、それを鑑賞者である私たちが目撃した時、今の自粛生活に置換され得ることでもあるだろう。
また、岡本の「I won’t be silenced.」、「I won’t go speechless.」。これらもまた、今の時代に積極的にアプローチをかけた作品だ。彼女が一貫してモチーフとしている ”個を示す人間の一部であった(ある)もの”、特に近年注視している”衣服”、あるいはさらに人体から距離感の遠のいたゴミ集積所のネットや、山中の廃材。そんな人間の抜け殻であるモチーフに、今の私たちの生活に必需となったマスクが含まれた。街中や道端にマスクが捨てられている状況は今までは見られなかった光景であるが、今やすっかりお馴染みとなってしまった。それを描いた彼女の作品は、ユポ紙(選挙の投票用紙として使われる紙)に水性アルキド樹脂絵具という手法で、非常に軽やかかつ鮮やかに描かれているものの、実際のそれらにはけして触れたくないという、えも言われぬ気持ち悪 さのような直感的な感覚がある。それは匿名で廃棄されたにも関わらず、維持され続ける誰かの生々しい個であるからに他ならない。
葛本の作品でも同じことが言えるだろう。彼は重力や光をビジュアル的なモチーフとしつつ、空間や大気といったモチーフをも内包させている。人間や自然が生命活動を行うためのささやかな動き。それに伴う関わり合い。そういった以前では極めて自然で無意識的であった活動は、いまやネガティブな意味で意識され、あるいは制限、抑圧され始めてしまっている。今回、彼は会場に付属する移動壁に合わせてインスタレーションを展開させた。作為的に設置された壁の隙間から覗き見る、時間帯や天候で変化していく光と影。重力に沿って形作られた発泡スチロールの彫刻や、霜が作り上げた絵画、その経過を写した映像。彼の手業がみせるスペクタクルは自然の力が積み重なって変化していく彫刻であると言えるだろう。そして彼のテーマとする作為と自然は、今の時代の中でより複雑に幾重にも交錯し、より一層現実的な神秘性を持ったドラマチックな体験として私たちに刻まれる。
今後、新型コロナウイルス感染症への特効薬が普及するなり、抑圧が可能となればそれに勝ることはない。とは言えウイルスは変異を続け、イタチごっことして長い付き合いになりそうな予感もある。これから先何を行うにしてもソーシャルディスタンスを保ち、衣服と同様にマスクをし、常に手指の消毒を行うこと。それが生活の一部となっていくのであれば、それに伴って彼らの作品も変異していくことだろう。そもそもアートは、あくまでも人間の作るものであり、時代を反映する側面を持つことは当然だ。これまでも、時代に沿ってアートの在り方は変容してきた。彼らが現在を生きながら、何を思い、考え、それを作品として提示するのか。気配を捉え、それを意識的に知覚しようとする行いに対し、私たちもまた新たな世界を発見・理解することで、今を生きて行く手がかりにできるのかもしれない。
藤樹の里文化芸術会館 学芸員 花田 恵理
2020.9 地元現代美術作家展『ニュー・ロケーション -維持される気配-』会場資料掲載文