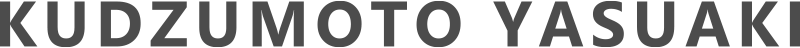里山と岡本さんについて“動的”ということから
何度かの里山での企画の実施を経て、僕は「里山」という言葉に“動的”な意味合いを強く感じています。それは「里山」という言葉には、単なる風景や地形の事だけではなく、人との関わりが保たれている“状態”が含まれているからです。それは何らかの“人の動作”でもあるので、そういった意味では動詞に近いニュアンスと言えるのかもしれません。
かつての里山が担っていた、生活に必要な食料や燃料を得るという役割は、今ではそのほとんどが失われました。生活に必要なもの自体が変化したことや、それらを揃えた「街」が整備されたことも、人が里山に近づかなくなった一因でしょう。人との関わりが無くなった里山は、人の目線からすれば荒れて、文字通り山になります。それも自然の姿として正しいのかも知れません。しかし、「もしも里山と関わる事が現代の生活に豊かさをもたらすとすれば」という命題のもと、芸術の立場から里山の価値を探る活動を行ってきました。
今日の里山の可能性を考えるうえで、「街」の存在は重要だと考えます。
前述のように、かつての里山の役割を街が補完した事で、現代の人々は里山に向かう必然性を失いました。本来そこにあった行き来は、里山のものを街に運び、消費するというものだったでしょう。一方で僕たちが里山で芸術企画を行う時、様々なものを「街」から「里山」に運びます。楽器や作品は勿論、物語や思想のような姿形を持たないものや、僕たちの身体そのものも運んでいると言えるでしょう。そうして運んだものが里山と関わる時、そこに新しい意味が生まれます。
例えばお芝居の最中に鳴き出したカラスは、物語の出演者となり、また音響として物語にアクセントを加えます。演技や演奏では再現性もさることながら、その即興性や一回性も重要であることは言うまでもありません。そして里山の“常に動き続けている状況”が作品とリンクする時、そのような自然と人為が動的に居りあった表現は、人の心に鋭く印象づきます。
「街」という「里山」との比較対象となる場を知っている僕たちは、意識的にも無意識的にもそれぞれの属性を住み分けて考えることが出来ます。農業のような長い時間をかけて行う事は、例えば農具が使用する中で色や形を変えていくように、その過程で「街」から来たものも「里山」に馴染んでゆくでしょう。そして芸術の場合、「里山」と「街」のものが、互いにその主体性を保ったまま場に共存することになります。それは見慣れた「街」のものを見直すきっかけにもなるでしょう。
里山での芸術企画の魅力は、作り手自身もそのような偶然の自然と人為の交わりの中に身を置き、その生成と消失をリアルタイムで体験できる事なのだと思います。僕自身についても、里山芸術企画の体験を経て自身の彫刻制作を精査し、その志向性を明確化することで、個展等の現在の活動を開始した経緯があります。
そのような幾度かの企画の実施を経て、絵描きの岡本さんに展覧会をしてもらいたいという考えに至りました。
もちろん身近にいて信頼できる人であるというのも理由のひとつです。それに加えて、岡本さんの絵から感じる動的な、或いは五感のすべてを駆使して物を見ているようなイメージは、里山の体験と似ているように感じるのです。
岡本さんの絵を初めて見たのは10年くらい前でした。遠くから見ると横たわる大きな顔が、近づいて行くと目の前で解体されてゆくように無数の鉛筆のタッチへと変貌しました。勿論作品が変化している訳では無く、鑑賞者が自らの足で作品との距離を変えることが、作品の見え方を全く違ったものへと変化させるのです。アクリルや油彩の作品でも、近くで見ると自由奔放に飛び交っているような筆致や色彩が、距離を取って見てみるとそこに人物の姿を浮かび上がらせます。
この「距離を取ると見えていたものが、近づくと見えなくなって別な存在として感じられる」という事を、僕たちの日常の人の捉え方に重ねると、「別な存在」とは肌のぬくもりや息遣いのような視覚以外で知覚している情報なのでしょう。
自ら動けない絵画でありながら、岡本さんの作品は鑑賞者のその場の動きや日常の知覚と連動し、動的に振舞うのです。
里山は絵画と違って、ひとつとて動かずにいるものはありません。風が吹けば木々が揺れ、羽虫たちは自由に曲線を描きます。草むらに潜む生き物はその身体の形に合わせて茂みを鳴らし、僕たちには見えない速度で緑は成長しているでしょう。それらのすべてを視覚のみで捉えることは不可能ですし、それこそ五感の全てを動員しても容易く私たちの受容の器はいっぱいになってしまいます。そのような絶え間ない無数の変化と運動は、どこか岡本さんの絵画の色彩や筆致の連続と重なるのです。
岡本さんの作品が、近寄ってくる鑑賞者にはその一つ一つの筆致や色彩にしか焦点を合わせさせないのに対して、里山の風景は距離を取って見ると、取り留めもなく連続し続け僕たちに焦点を合わせさせません。そして風景に近付くにつれ、次第にその中に特定の植物や地形、枝や葉の形、生き物の姿など、そこにあるものがはっきりと見えてきます。岡本さんの作品と里山の風景は「距離と焦点の関係」という部分で真逆の性質を含みます。そのような里山の風景を取材し、モチーフとした岡本さんは、「作品」と「風景」のそれぞれが持つ距離感の中間を探るようにして絵画制作を行ったようです。
岡本さん曰く、「(手を顔の横で開き、前方に広げていくようにして)いわゆる風景画を描く人のようには私はものを捉えられない、(顔の前で手のひらの内側に球を作るようにして)適切な距離を取ってこう、何らかの対象を見つけないと描けない。」
そうして岡本さんが風景の中に見つけたのは人の痕跡でした。焚火の跡や、キノコ栽培の榾木にかけられたネット、地面に打ち込まれた木に結わえられたピンク色のテープなど、一見風景の中に埋もれているようなものたちを掘り起こすように、岡本さんは画面に描き出しています。こうした岡本さんの制作行為もまた、人間と里山との調和的な関係のひとつと呼べるのではないでしょうか。
また、近年岡本さんが重用しているユポ紙とアルキド樹脂絵具が生み出すテクスチャーも里山の動的なイメージと繋がるものがあります。端的にそれは水のイメージです。選挙の投票用紙にも用いられているユポ紙はポリプロピレンから生成されたフィルムであり、耐水性に非常に優れ吸水性を持ちません。その為、一般的な水溶性の絵具では定着しませんが、これに対しアルキド樹脂絵具は水性ながら抜群の定着力を持ち、ユポ紙上にも定着します。これらの画材の組み合わせで生まれる、未だに水を含んでいるようなテクスチャーは、水の存在や今にも流れ出してしまいそうな流動性を感じさせます。このような画材の効果がこれまでの筆致や色彩と相まって、存在することとその不安定さのような両義性を画面に生み出しています。岡本さんの作品は基本的に洒落た空気を纏っていますが、そうした側面では水の流れに諸行の無常を読むような、仏教的な価値観も垣間見られるでしょう。
そうした人物そのものをモチーフとする時期を経て、最近の岡本さんは“脱がれた衣服”を描いています。
日常的な空間であるベランダやフローリングを背後にして、きっと少し前まで服の内側にあった不在の身体を仄めかすことで、“肌触り”や“所作”のような触覚性の強調を岡本さんは試みています。衣服が「人体と空間の境界」とすれば、里山は「人為と自然の境界」にあたります。私たちが衣服を介して社会や風土、気候条件との適切な触れ合いを生み出すように、里山という場所は人間と自然の適切な距離感を考え、提示することに適した場なのかも知れません。
例えばスケッチのような取材をもとにして絵を描くことは珍しいことではありません。しかしここまで記したように、岡本さんの制作に対する問題意識や使用画材の性質は、里山という空間を表現することと、もれなく結びつくのではないでしょうか。
今回の展覧会によって、里山から街に“芸術”を運ぶ事と、それをまた里山に返す事、そうした“動的な循環”をこれから維持してゆくことが“里山と芸術”を考える次のステップのように感じています。
まだ秋までは少々時間があります。今回の展示を経た頭と身体で里山との関わりを更新してゆきたいと思います。
2019.6「さとやま-ギャラリ / SATOYAMA GYARARI Exhibition」会場資料掲載文
works|https://kudzumoto.com/works/work-satogyara/